
JIROです!
今回は初心者向けにアクアテラリウムの『作り方』や『レイアウト方法』について紹介します。
アクアテラリウムでは飼育できる生き物の種類も増えるので、アクア生活がもっと楽しくなること間違いなしです!
それではさっそく参りましょう!
アクアテラリウムとは?

まずアクアテラリウムとは簡単に説明すると陸上部分のあるアクアリウムです。
飼育する生体によって『水位』を変更することで、魚や両生類などの様々な水辺の生き物を飼育できるようになります。
また『水中』と『陸上』の世界があるので、水槽レイアウトの幅もグッと広がります。
ちなみに植物インテリアとしても、水草アクアリウムより維持管理が楽になるメリットもあります。
アクアテラリウムに必要なもの

アクアテラリウムを始めるために必要なものは大きくわけて5つの要素があります。
それは『飼育容器』・『レイアウト素材』・『生き物&植物』・『照明』・『水の供給システム』です。
多くの点で『アクアリウムと共通』しますが、アクアテラリウムならではのポイントもあるので順番に紹介していきます。
アクアテラリウム水槽の選び方
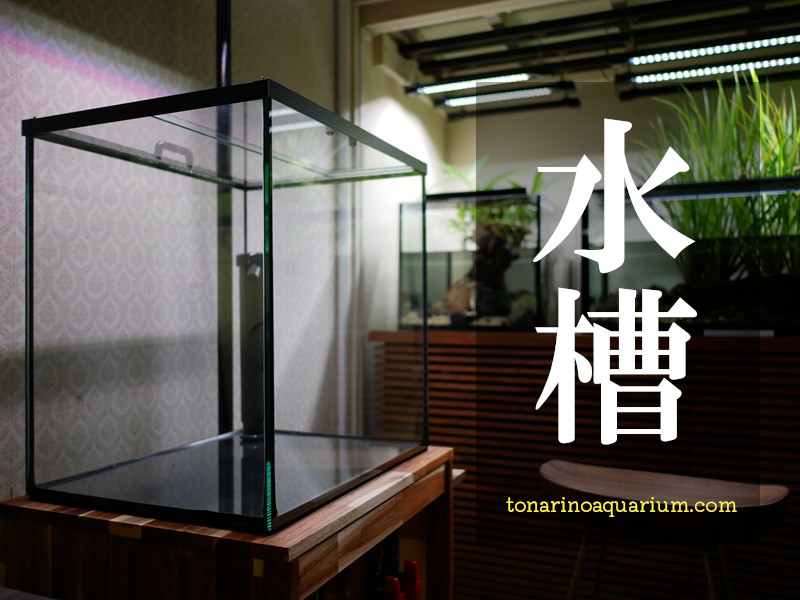
まずは『飼育容器』となるアクアテラリウムの水槽についてです。
アクアテラリウムでの水槽の選び方はサイズだけでなく『仕様』も考えておく必要があります。
水槽の仕様については『飼育する生体』や『レイアウト』によって決めることができます。
水深の深いアクアテラリウム

まず水深のあるアクアテラリウムを作りたい場合には、アクアリウム用の一般的なガラス水槽を使用します。
水深のあるアクアテラリウムでは『魚』の飼育はもちろんのこと、脱走されないようなフタなどをつければ『アカハライモリ』や『サワガニ』などの飼育も可能です。
一般的なガラス水槽はコスパが良く、様々な生体の飼育やレイアウトに適応するため、アクアテラリウムにおいても一番オーソドックスな飼育ケースになります。
前面斜めカットフレーム水槽

植物を中心としたアクアテラリウムであれば、水槽フレームの前面が斜めカットされた水槽なども使用できます。
『飛び出し』や『脱走』されやすいケースなので、生き物の飼育には不向きですが、前面ガラスが低いためメンテナンスなどが簡単になるので、植物をインテリアとして飾るには便利な水槽です。
水位の低いアクアテラリウム

水位の低いアクアテラリウムの場合は、爬虫類用のケージを使うことも出来ます。
爬虫類用のケージは水槽に比べて『通気性』が高く、『脱走防止策』や『メンテンナンス性』などに配慮された優れた製品です。
フタやロック機能など万全なので『イモリ』や『カエル』などの脱走し易い生体の飼育にとてもオススメです。
ただし爬虫類用のケージでアクアテラリウムをする際は、水を入れることが可能な製品であることを確認しておきましょう。
レイアウト素材

次は水槽を彩るのに欠かせないレイアウト素材について紹介します。
レイアウト素材とは『流木』や『石』などのことで、これらを組み合わせることでアクアテラリウムを作っていきます。
またその際には『砂利』・『ソイル』といった底床なども必要となります。
使い方

レイアウト素材は見た目が良くなるだけでなくアクアテラリウムの陸上部分を作る時にも役立ちます。
石や流木は『大きなもの』であればそのまま入れて陸上にすることができますし、『小さなもの』でも組み合わせることで陸地を作ることができます。
陸上部分のレイアウトの際に隙間がある場合は『砂利』などで埋め立てたり、植物など育てるところには『ソイル』などの少し肥料の入った底床なども使ってレイアウトしていきます。
コルク
アクアテラリウムの生き物や植物について

アクアテラリウムの主役は『生体』や『植物』です。
なのでアクアテラリウムでは飼育する生体を決めることで、『レイアウト』も考えやすくなります。
ただ生体によっては植物と育てるのが難しい場合もあるため、生き物ごとの『アクアテラリウムとの相性』について紹介しておきます。
魚とアクアテラリウムの相性

まずは魚についてですがアクアテラリウムとの相性は抜群です。
水位は必要になりますが、陸上の植物への『食害』や『踏み付け』などによるダメージの心配がありません。
またエビなど水中から出ることのない生き物も同様に陸を荒らされることがないため『相性はとても良い』と言えます。
イモリとアクアテラリウムの相性

次は水中生活を主とするアカハライモリについてです。
アカハライモリは肉食なので植物を『食害』したり、あまりパワーもないのでレイアウトを壊すことが少なくアクアテラリウムとの相性は『比較的に良い』と言えます。
ただ陸があればたまに上がってくるので、植物は踏み付けなどのダメージを受けることがあるので、繊細な植物との共存はやや難しくなります。
カエルとアクアテラリウムの相性

カエルなどについても相性が良くアクアテラリウムで飼育することが出来ます。
イモリ同様に食害の心配はないですが、大きな種になると、力が強くなってレイアウトや植物を破壊しやすくなるので、小さい種の方がオススメです。
また『吸盤タイプ』のカエルはくっつくのでガラス面が汚れやすくなるという面があります。
カニとアクアテラリウムの相性

そしてサワガニなどの小さなカニであればアクアテラリウムでも飼育は可能です。
ただ、小さくてもカニは掘る力があるので、レイアウトしだいでは徐々に崩れていくことがあります。
また植物によっては食害を受けるので選定に注意が必要です。
カメとアクアテラリウムの相性

カメを飼育する場合はアクアテラリウムの相性はあまり良くありません。
カメは雑食性の種が多いため植物を『食害』されやすく、小さい種でもある程度の『パワー』があるため植物やレイアウトを壊しやすいです。
ただ特性をしっかり理解すれば出来ないこともないので、飼育に慣れている方であれば楽しいチャレンジになるはずです。
ヘビ

ヘビは種類によってはできるかもしれませんが、基本的にアクアテラリウムの相性は難しいと言えます。
ヘビもカメ同様に基本的にレイアウトへの負荷が大きく、わざわざアクアテラリウムで飼育するケースがほとんど見ません。
ただ『ミズヘビ』のような水棲のヘビであれば、アクアテラリウムでも飼育しやすいかもしれません。
生き物を飼育しないアクアテラリウム
ちなみに当然ですがアクアテラリウムで一番維持管理しやすいのは生き物を飼育しないアクアテラリウムです。
生き物は居たほうが楽しいですが、インテリア重視であれば飼育しない方がメンテナンスもずっと楽になります。
照明

そして次は植物を育てるために欠かせない照明について紹介します。
照明の候補にあげられるのは『LED』や『蛍光灯』などになります。
照明の色温度は大体『5000~10000K』くらいまでのものを選びます。
蛍光灯

蛍光灯を使用する場合は、一般的な昼光色タイプの電球をクリップライトなどに取り付けて照射することで植物を育成できます。
蛍光灯の特徴としては、光が回り込みやすく『影が出来にくい』ため、レイアウト全体が明るくなりやすいことが挙げられます。
LED

LEDを使用する場合は、『植物育成用』や『水草アクアリウム用』などの専用に開発されたLED製品などもオススメです。
LEDの特徴は、『省エネルギー』・『高寿命』など経済的なことや、レイアウトに陰影のコントラストが生まれやすいことなどが挙げられます。
またマルチカラーLEDタイプのように、色を自由に変更できるタイプなどもあります。
ゼンスイマルチカラーLED
照射時間

照明の時間は、1日6時間~10時間程度を目安に管理します。
電源のON/OFFは手動で行うと手間なので、『プログラムタイマー』や『スマートコンセント』などを使って自動化しておくのがオススメです。
プログラムタイマー
植物に水を供給するシステム

そしてアクアテラリウムならではで考えておかなければならないのが、陸上部分の植物に水を供給する方法をデザインしておくことです。
水の供給は『手動』もしくは『自動』で行いますが、様々な方法があるのでここではいくつかの例を紹介しておきます。
手動で給水

まず手動で給水する場合の代表的な例が霧吹きによる水やりです。(1日数回など)
乾燥に弱い植物の場合難しいこともありますが、マメに手を掛けられる人であればオススメです。
自動で給水

次に自動で給水したい場合は水槽に水中ポンプを入れて『分水器(ティポイント)』などで陸上部分に排水する方法があげられます。
分水器(ティポイント)とは、エアチューブなどと使用して陸上部分の各所に排水できるようになる給水管パーツです。
また『外部フィルター』などを使う場合でも、分水器をつければ同様のことが行えます。
この場合、常に水やりをしている状態になるので、使用する植物は『水草』や『水耕栽培できる観葉植物』など、湿り気がある環境が得意な植物がオススメになります。
※ポンプで水を汲み上げるパターンについてはこちらでも紹介しています⇒アクアテラリウムで水を分水器で循環させる方法ベスト3!
ティポイントセット
植物に浸食させる

そして何も手をかけない方法としては水草などを水中葉から育成して『陸上部分を浸食』させる方法もあります。
例えば時間は掛かりますが、陸地との水際でウィローモスを水上化させると徐々に『水分を運びながら陸上に浸食』してくるので、その上で別の植物を育てることも可能です。
その他には簡単な方法として、水位と同じくらいの陸地を用意して、水耕栽培できるような観葉植物を『水際のみで育てる』というのも方法もあります。
※ここでモスの上で育てている植物はセキショウなどです。
ウィローモス
セキショウ
アクアテラリウムの作り方
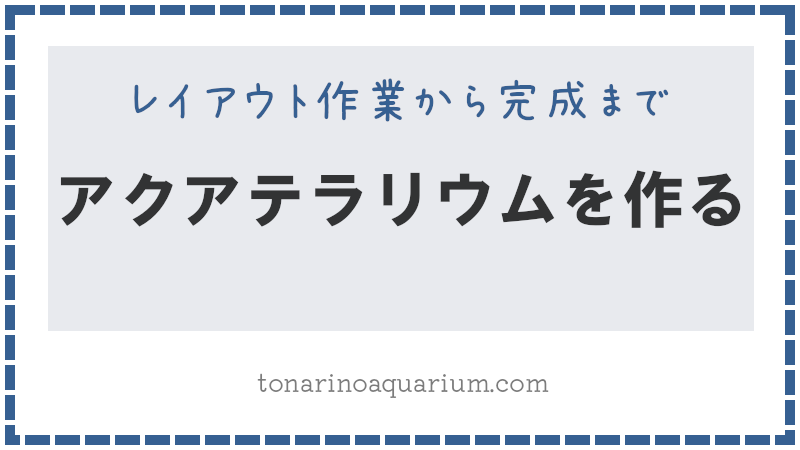
それではアクアテラリウム作りの参考までに1つ実際の製作例を紹介しておきます。
ここでは通常のアクアリウム用の水槽を使ってアクアテラリウムを作っていきます。
アクアテラリウムのレイアウト

まずはアクアテラリウムのレイアウトです。
飼育する生体は『アカハライモリ』で、水位の低いアクアテラリウムを目指してレイアウトしました。
陸上部分は『石』を土嚢の様に使って、さらに砂利で埋め立てて作っています。
『流木』は複数を組み合わせて、結束バンドで固定しています。
埋め立てる時のポイント
埋め立てる時のポイントは、砂利などが流出しにくくなるよう『しっかり堰き止め』たり、『大き目の粒の砂利』を使うなどして対策しておくことです。
また飼育する生体によっては、動かされないよう大きな石を使用する必要もあります。
アクアテラリウムのシステム

ここでの水を供給するシステムはポンプを使い『分水器*』で陸上部分に自動で排水する方法を使っています。
分水器にはエアチューブを付けて、各所に回して排水するようにします。
また給水に関する部分は、一般的な『プラ製の排水栓カゴ』をカバーにして埋め立てて隠蔽するようにしました。
※ここではティポイントの代わりに、自作した分水器を使用しています。
排水栓カゴ
アクアテラリウムの植栽

あとは『レイアウトの土台』と『水の供給システム』が出来たら、アクアテラリウムの植栽していきます。
陸上部分の表層には少し『ソイル』を追加してあります。
給水の一部は流木の上からかけ流すようにしているので、水がビチャビチャとしぶき*を上げないように、ウィローモスで『水を誘導』しながら水槽全体を潤わせています。
植栽が完成したら、あとは時間がレイアウトを完成させてくれるのを待つだけです。
※『水しぶき』が上がる所はいずれガラス面が白く汚れるのでなるべく抑えるようにしておきます。
アクアテラリウムのレイアウトの完成

その後、植物が育ちアクアテラリウムが完成です。
ここで『最後』に今回の主役となるアカハライモリを投入します。
植物が育つ前に生き物を入れると踏まれたり動かされたりして『育成に支障』をきたす場合があるため、基本的に生き物は植物が『活着』したり『根付いた後』で入れるようにします。
あとの基本的なメンテナンスはアクアリウム同様に定期的にカルキを抜いた水で『水替え』をするだけです。
ちなみに今回のアクアテラリウムに使用した植物は、ウィローモスの他には『アジアンタム(流木の上)』や『ベビーティアーズ(陸上部分)』『マメヅタ』などになります。
アジアンタム
ベビーティアーズ
マメヅタ
最後に

アクアテラリウムは『生き物』・『レイアウト』・『植物』の組み合わせ次第で、様々な生き物を飼育できます。
作り方のイメージができれば、あとは実践あるのみです。
力不足ではありますが、アクアテラリウムの魅力を少しでも紹介できていれば幸いです。
以上、アクアテラリウムの作り方についてでした。
それではよいアクアテライフを。
アクアライフ












コメント
初めまして。
イモリ水槽で「アクアテラリウムのレイアウトの完成」の画像内の、
右側陸地部分と樹上に植栽している植物は何でしょうか?
差し支えなければ教えてください。
よろしくお願いします。
はじめまして!
ご質問いただいた植物の件ですが、流木上の植物はアジアンタムです。
右の陸上部分の大部分を占める植物はソレイロリア(ベビーティアーズ)だったと思います。